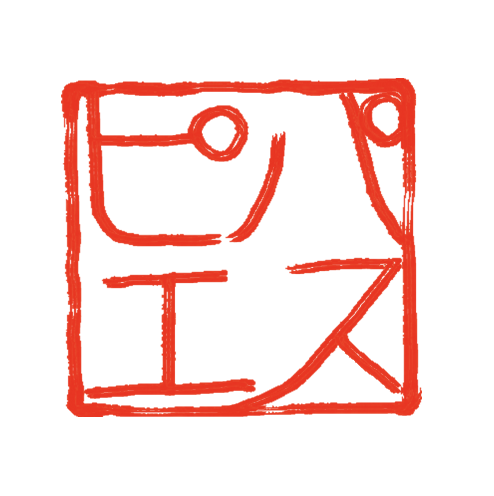OFFICIAL INTERVIEW

パスピエに完成はない
――ニューモードに突入した6枚目のフルアルバム『synonym』(シノニム)は、また新たなパスピエに出会わせてくれる作品だ。結成10周年を経て、すでにバンドとしての「型」を獲得していながら、その枠には留まらず、新たな音を生み出した今作は、現時点でのパスピエの最高到達点であることは間違いない。だが、決して終着点ではない。2010年代のパスピエから2020年代のパスピエへ。鮮やかに橋渡しをする重要な作品になっている。
バンドとしてひとつのエポックとも言うべき今作について、長年パスピエの活動を追い続けるTBSラジオのプロデューサー宮嵜守史氏を聞き手に迎えて、メンバーと語り合ってもらった。宮嵜氏とバンドの関係性だからこそ引き出された4人の自然体な発言から、『synonym』の本質に迫った。
今回「また作るぞ」ってなったときに、どういう目的を持って、盤というもの、音源っていうものを出すのかを考えさせられたんです。(成田)
- ――今回アルバムを聴かせてもらって思ったことを、メモしてきたんですよ。
成田:ありがとうございます。
- ――1曲ずつ感想を言ったほうがいいかな?
成田:宮嵜さんはこれまでのパスピエの音楽も聴いてくださっているじゃないですか。まず、全体を通しての感じって、どうでしたか?
- ――僕、前作『more humor』からガラッと変わった感じがしたんですね。パスピエの雰囲気が。
大胡田:そうですね。
- ――で、今回のアルバムで言うと、特に1曲目の「まだら」とかは、すごくディープな曲というか。それは何があったのかな?って思いました。
成田:ああ。僕らが新しい体制になって初めて出したフルアルバムが前作の『more humor』だったんですよ。そこから、新しいエッセンスが入ってきて、俺ら自身も「変わろう」って意識してたんです。だから、「変わったな」って思っていただけるのはうれしいですね。
大胡田:うん、そうね。
露崎:『more humor』は、「ONE」がリード曲で、それを生み出すために苦労した部分があって。それが軸になって、今作につながってる部分はあったと思いますね。
三澤:あと、『more humor』までは「10周年」っていう括りのなかにあったので。それを抜けて、気持ちを新たにというか。自由になったところで作ったから、印象が変わったのかもしれないですね。- ――大人な感じがするんですよね。しっとりさが加わったというか。
成田:バンドを10年やってると、いろいろ変わるじゃないですか。自分たちも周りも変わる。そういうなかで、昔作った感じをそのままいまやろうと思えば、できると思うんです。でも、それが自分たちの思う「いい鮮度」で伝わるかどうかは難しくて。 それは自分で勝手に思ってるだけかもしれないけど、常にいま自分たちがやっておもしろいことをやろうっていうのはあるんですよ。
大胡田:長いことやってきたことで、「私たちがやったら、なんでもパスピエになるな」っていうところまではいったなと、私は思ってるんです。でも、そこで終っちゃうと止まっちゃう。そこより先にいく方法を、『more humor』ぐらいから考えてたんですね。で、今回のアルバムでは、「これだったらパスピエ」っていうものから、「新しいパスピエ」を作っていく。そこに触れられたんじゃないかなって。
三澤:パスピエの幅が広がったなって思いますね。- ――うん。『more humor』では、「俺たち、こんなんもできるんだぜ、あんなんもやってみるぜ」って見せてくれたけど、今回の『synonym』は、そっちの方向にオセロの盤面がババババッて一気に変わった感じ。新しい場所がパスピエの領地になったっていうか。
成田:今回は6枚目のフルアルバムになるんですけど、前回の『more humor』が終わって、今回「また作るぞ」ってなったときに、どういう目的を持って、盤というもの、音源っていうものを出すのかを考えさせられたんです。
- ――うん。
成田:最近すごく思うのが、クリエイティブって、3つの承認欲求があるなって。まずは、自分自身のハードルを越えること。「これは納得いったぞ」って、自分で承認したい欲求ですね。 あと、より多くの人に聴いてもらいたいっていう大衆的な承認欲求。で、最後のひとつの表現が難しいんだけど、自分たちに近しい人。それは昔から聴いてくれてる人だったり、自分たちの側にいる人だったり。 そういう人に「やっぱりパスピエの音楽おもしろいな」って思われたいっていうか。
- ――うんうん。
成田:その3つって、どこまでいっても、終わりがないんですよ。3つが平均的である必要もないし、どこか突き抜けてれば、それでもいいし。 たぶんデビューしたての頃って、自分たちが何者でもない状態から、とにかく大衆に届けたいから、大衆の承認欲求が強く出てた時期もあって。 でも、作品を出していくうちに、もっと自分たちがやりたい音楽が出てきて、また違う承認欲求が増えてきて作ってきたのが、『more humor』とか、今作なんですよね。
- ――話を聞いてると、『more humor』では、まずひとつの承認欲求を突き詰めて、今回の『synonym』では、2個目、3個目に広がってるように感じる。
-
成田:ああ、そうかもしれないです。
露崎:作り終えてみて、今回は全然ベクトルが違う喜びがあるんです。『more humor』で足りてないわけじゃなかったけど、前作で突き抜けてた部分とは、また違う部分で突き抜けた承認欲求まで届いてる。これが評価されたら、すごくうれしいなって感じる作品になったかなと思います。
三澤:時期的にも、すごくいろいろなことを考えたんですね、このアルバムの制作中って。世界が大変なことになってるなかで、「音楽やってていいのかな?」っていうところまで考えたんです。そしたら、ギターを弾かないでみようかなって、実験じゃないですけど……。 でもやっぱり気づいたらギターを弾いてるんです。一同:あははは!
三澤:だから、少なくとも自分にとって、音楽って必要なものなんだなって再認識して。自分がそうだったら、聴いてくれる人もそうだろうっていう考えにもいたって。まあ、そういうなかで生まれたアルバムではありますよね。
- ――制作時期は、コロナ真っ只中?
三澤:ですね。
- ――じゃあ、ちょっといつもとはまた違う立ち戻り方をしたっていうか。
成田:レコーディングのスケジュールも紆余曲折しながらやってましたね。でも、結果的に2020年に出せたっていうのはよかったなと思うかな。
露崎:そうだね。
三澤:こういうなかで作るのは、決して悪い影響ばっかりじゃなくて。本当に制作に集中できたから、そこにすべてをかけられたのは良かったと思いますね。- ――作業的には各自が家でやる、みたいな?
露崎:そうですね。普段自分がやってなかった作業も増えてきて。この制作を通して成長できたことが多かったから、それが詰め込まれてる作品にはなりましたね。
- ――じゃあ、ここからは1曲ずつ、メモを見ながら感想を伝えていきます。さっきも言っちゃったけど、1曲目の「まだら」はディープ。“都合の良い善悪 ぶらさげて街の中へ”っていう歌詞が痛え。僕ね、大胡田さんの歌詞でいつも反省するんですよ。
一同:あはははは!
大胡田:え、良いこと? 大丈夫ですか!?- ――それはマイナスじゃなくて。「あ、たしかに、俺、ここを忘れて生きてたかも」みたいな。たぶん大胡田さんは、世の中とか社会を俯瞰して見てる感じがするんです。自分の心のコックピットで見えてるところが、人より遠い。大気圏ぐらいまでいってるというか。
成田:遠いですねえ(笑)。
- ――だから、「まだらの」歌詞を聴いて、「俺、都合の良い善悪で、自己を肯定して生きがちだな」と思って。それは、そういう人を見て思いついたのか? 自分がそうだって思っちゃったのか?
大胡田:世の中って、自分に関心がなかったりしても、すごいスピードで変わっていくなと思ったんです。政治も、地球の環境とかも、今回のコロナも。 そういうことに対して、不思議に思ったり、驚いたりしたら、もっと素直に反応したほうがいいなって、ここ何年かで思ったんですよね。そういうのが得意な方っていらっしゃるじゃないですか。 みんなを納得させるインフルエンサーの方とか。でも、私はそういうタイプじゃないと思ってて。歌のなかで、「これは問題だ」とか、「これはどうなの?」っていうのを差し込んでいきたいなって。 頭から最後まで、そういう言葉じゃなくても、歌のなかに言葉が自然に入っていて、誰かの意識を変えられるような歌が書けたらいいなって思ってたから。うん、宮嵜さんの言葉はけっこううれしいです。
- ――“泣きながら生まれて 泣きながら生きるの”っていう歌詞もよかったです。
大胡田:私も。
- ――続いて、「Q.」。メモによると、「イントロこれこれ!」なやつ。「ララレイララレイヤ…」この呪文なに?って書いてる。
一同:あははは!
- ――これぞパスピエですね。これまでパスピエが作ってきた型があるとしたら、その型のうちのひとつの曲って感じがしました。
三澤:うん、そうですね。
成田:さっきの承認の話につながるかもしれないんですけど。作品を出すたびに、自分たちのなかの自己承認のハードルが高くなってて、ずっと違う道を選び続けてきたんですよ。特に『more humor』までは。それが10年やって、1周したところはあって。「Q」は、聴く人によっては、「パスピエ印」を感じられると思うけど、そういうのも、僕らはまた新鮮な気持ちでやれるようになってるんです。
露崎:たしかに。1周してまた新鮮な気持ちでやれたっていうのはあるよね。- ――いまの話を聞いて、みんなはすげえ幸せな仕事をしてるんだなって思った。4人ってバンドでアーティストじゃないですか。その人たちって、ひとりよがりで作っていい権利を託されてる気がするんですよ。 「これはこういう曲だ」って作ったとしても、聴く人がそう受け取らない場合もある。
露崎:うん。
- ――で、そこが一致してもうれしいし、一致しなかったとしても、その創作物に向けて、考えを巡らせてくれただけで幸せというか。
三澤:たしかに。世に出た瞬間に、半分自分らの曲じゃなくなるから、聴いた人がいいと思えば、全然それでいいんだろうなって。 「パスピエっぽい」っていう定義も、人によって様々だし、それこそ「Q.」は僕ら的には新しい気持ちで作ったけど、「パスピエっぽい」って思われるなら、それはそれでいい。
- ――次にいきます。「現代」。俺、これがいちばん好きかもって書いてあります。
一同:おー!
- ――ただ、「これがいちばん好きかも」シリーズが、このあとも続きます。
一同:あはははは!
- ――いろいろメモをとりながら聴いてたんだけど、「あ、これ、やっちゃいけないな」と思ったのが、他のアーティストを引き合いに出して、「〇〇っぽい」って、なんか嫌だなと思ったんです。 「美味しいものを、美味しいものでたとえるのは良くない」って、グルメリポーターが言ってたのが頭をよぎって。だから、それをやめとこうと思って。
大胡田:気になる(笑)。
成田:全然いいですよ。- ――じゃあ、言うけど。俺、小西康陽が大好きなんですよ。で、なんかピチカート・ファイヴっぽい。初期のころのピチカート・ファイブの匂いを感じた。
成田:なるほど、その感覚はうれしいですね。
大胡田:私はスティーリー・ダンっぽいなって。勝手に自分から「〇〇っぽい」を出してるけど(笑)。そこらへんのコードワークとかリズムの感じが好きなんですよ。AORというか。- ――うん。たしかに、YACHTとかね。
あと、「現代」に関しては、シンセのパワーを改めて知った。 成田:これ、最初はめっちゃフュージョンっぽく、テクニカルに難しいことの応酬だけで作ろうとしてて。最終的にストリングスとかバイオリンみたいなシンセサイザーを入れて、ガラッとイメージを変えたんです。アルバムタイトルの「synonym」ともつながるんですけど、どれもつながってるんですよね。AORと渋谷系のニュアンス的な部分だったりとか。僕らって本当に雑食でいろいろなものが好きなだから、そういうのを混ぜた結果、生まれた曲だろうなっていうのは思いますね。
大胡田:私は、デモを聴いたときと完成したときの印象が違くて。思ったより日常に寄り添ったというか。日常のなかにあって陰鬱じゃないものになったなって思った。タイトルもそうだし。
露崎:難しい曲っぽく完成するかなと思ったら、きれいな曲に仕上がったから、「すごい化けたな」っていう感じはありますね。
三澤:この雰囲気はいままでなかったんじゃないかな。
成田:あんまりないかもね。
雑食でいろいろなものが好きなだから、そういうのを混ぜた結果、生まれたのが「現代」だろうなって。(成田)
- ――続いて、「SYNTHESIZE」。これ、イントロのポンッていう音。どうして、これにしたの?って気になりました。マリオコインっぽい感じというか。特徴的ですよね。
成田:曲作りって、ピアノを弾いたりとか、鼻歌で作ったりとか、最初はメロディラインだけが浮かんでできたりもするんですよ。 それを1回シンプルなバンドっぽい音源にして、メンバーに聴かせるんですけど。そのときにパソコンでざっくりイメージを作って、 その音に近い音を本物のシンセサイザーで録りなおしたりするんですね。でも、「SYNTHESIZE」は、最初に送ったイメージになかなか近づかなくて。同じメロディラインを、6パターンぐらいの音で重ねて録ってるんです。
- ――そっかあ。「SYNTHESIZE」は90年代に聴いてた音楽を思い出す感じもあった。景気がよかった頃の街のネオンが光ってて、みたいな雰囲気が気持ちいいなって。
三澤:音色はだいぶこだわりましたね。この曲は。直接会えない時期だったので、夜な夜な4人でZOOM会議を何日間かやって。「あそこのイントロ、テンポを1あげようか」っていうのを、3日4日やって完成した曲なんですよ。
- ――そういうZOOM相談もあるんだ?
三澤:新しいコミュニケーションの仕方でしたね。
大胡田:このとき、本当に会えない時期だったもんね。
三澤:新鮮でおもしろかったです。- ――4人がZOOMで話してるのを想像すると、ZOOMって話す人の枠が黄色くなるじゃない? お互いに間合いを探りそうな気がする。
三澤:そのとおりです(笑)。
成田:すごい不思議な空間ですよね、ZOOMって。それこそ1回、ZOOMで音を出して、セッションとかもやろうと思ったけど。
大胡田:やったねえ。
成田:どうにも、コンマ1秒ズレたりとかして、できないんですよ。- ――5Gよ、早くこい。
成田:そうそう、思いました(笑)。
- ――続いて、「プラットホーム」。温かいイントロ。いまの季節にぴったりじゃんと思ったら、まんまと冬の曲だった。
大胡田:これもね、脈々と続くパスピエの流れを感じますよね。
- ――ファン目線で言うと、「最終電車」の続編なのか、アナザーストリーなのか、そういう雰囲気。
成田:イントロを作った段階で、その感じはあるだろうなと思って。タイトルも関連してますしね。
- ――メロディもキャッチーで。
大胡田:たまにやるやつだよね。真面目にポップスする、みたいな。本気でそっちに全部かける。
- ――途中のストリングスもいいです。
三澤:ストリングスを入れて、完成型の印象が変わった曲ですね。もうちょっと小さめのシチュエーションの曲になるかと思ったら、けっこう壮大な感じで。ストリングスのパワーはスゴいなって。
大胡田:これはストリングスがめっちゃいい。- ――続いて、6曲目の「oto」。これも、メモをそのまま読むと、“ムズそう”“パスピエの意地とプライド”ライブでどう演奏するか見たいって書いてます。
成田:これはもう1個テーマがあって。年明けに「まだら」をやって、その次ぐらいに出したやつかな。
露崎:そう。構想的には、「EYE」(読み:いわい/2020年2月16日に昭和女子大学 人見記念講堂で開催した十周年特別記念公演)が終わって、次どうしようか?ってなって。
成田:で、ちょうど3月4月で、ライブもできないし、外にも出られないってなって。音楽を作ることしかできなくて。そこで、「2020年5月5日がデジタル数字表記(20200505)で回文の日だね」って気づいたんですよ。 で、「回文の曲を作ろう」っていうので、この曲は、歌詞が逆から読んでも全部同じになってて。メロディもドラムフレーズも全部左右対象になってるんです。- ――えー!? それ、ネタばらししていいの?
成田:いいです、いいです。一応、リバース再生って、歌詞ではローマ字ひっくり返しにしないと、逆再生の回文にはならないんですけど。さすがにちょっとそれだと難解すぎるなって。歌詞は見た目上の回文になってて、音楽的には、逆再生しても同じにはなってます。
大胡田:歌詞も逆再生でやりたかったなあ。
成田:ドラムのアタック音とか、その余韻を逆再生すると、サーッみたいな音になるんですけど。ひっくり返しても、合う音だねって、この曲には。
露崎:さっきの承認の話で言うと、自己承認欲求の極みみたいな。
成田:そうそうそう(笑)。
大胡田:気づかない人は気づかないっていう。- ――すごい!すごいなあ。
成田:これをひとつの楽譜にしたら、右から読んでも左から読んでも、全パート一緒、真ん中で折り返しになる。
- ――パスピエって、そういう趣向があるよね。癖(ヘキ)っていうか。
成田:ありますねえ。これを回文の日付の日に出してやるっていう、スーパー自己マン。
一同:あははは!- ――細かすぎるから気づかなくてもいい、自分たちが満足すればいい。
三澤:それもあって、真ん中にあるんですよね。曲目の。
- ――そっかあ。みんな好きなの?そういうのを考えたりするのって。
成田:きっかけは大胡田が回文のタイトルをアルバムにつけた所からで。『わたし開花したわ』であったり、『演出家出演』であったり、『ONOMIMONO』であったり。でも、そこから、しばらく離れたんだよね、その回文みたいなのは。
大胡田:そうだね。
成田:で、たまたま2020年5月5日があったっていうだけなんです。それで、自分たちがやってきたことの延長で、何かおもしろいことができないかなっていうところで。- ――デジタル表記にしたときにね。よく見つけたね、それ。
成田:たまたまですね。
- ――俺だったら、とてつもなく何にもすることがない日でも気づかないよ。
一同:あはははは!
- ――続いて、「真昼の夜」。先にシングルが出てたよね。これはイントロのドラム。あと、不気味なシンセ。そしたら、歌詞が“ポンパポンパ”。「真昼の夜」も意味わからない(笑)。あと、メモには「ニ律背反、表裏、異世界」って書いてあります。 これはパスピエのキーワードのひとつですよね。タイトルもそうだし。
成田:”バンド”というロックと近しいところにいるフォーマットって活動してますが、僕らはロック的な表現をやりつつも、でも、女性ボーカルで、声も高くて、みたいな、常に捻じれのなかにいるバンドだと思ってて。シングルだったり、リードを出すときって、絶対にそこは1回よぎるんですよ。いま、自分たちは何を出すべきかなって。
露崎:うんうん。
成田:全然ベクトルは違うけど、「まだら」もそういう一面があるし。「真昼の夜」に関しては、『more humor』ぐらいから、アップテンポからは一歩引いてた時期があって。速い、捲し立てるような曲じゃなくて、別の視点でやってみようかなって考えてたんです。ゆったりなんだけど、力強いとか。で、そこからいろいろ経ていくうちに、知識とか引き出しが増えてきて、いままたアップテンポの曲をやったら、どうなるかな?みたいなのがきっかけかな。
大胡田:「真昼の夜」は、一般的にアップテンポって言われて思い浮かぶ印象とはちょっと違うよね。言ってくださった「異世界感」というか。緩急がすごくて、すごい不思議な世界なんです。
「oto」は、自己承認欲求の極みみたいな曲です。(成田)
- ――続いて、「Anemone」。これもね、最初にイントロを聴いて、パイプオルガンで演奏したらすごいんじゃないかって思ったら、まんまと最後のアウトロに入ってました。
一同:あはははは!
- ――教会感があるじゃんって。
成田:最初、仮タイトルが「バッハ」だったもんね。
大胡田:うん、何て言うの? バロック?
成田:バロック。クラシック感があるんですよね。- ――あるね。メロディが切なくて、日本のポップスの作る切なさを感じた。
成田:この曲は、自分の意地というか。クラシックを取り入れたポップスって、いろいろなかたちがあるんですよ。 クラシックの楽曲のメロディをそのまま切り取って、別の楽器で演奏したりだとか。まんまクラシックの曲を歌ものとしてアレンジしたり。 自分も小っちゃいころからクラシックに関わってきた身として、自分なりにそういうエッセンスを出しながら、ポップスを作りたかったんです。もちろん、いままでもやってこなかったわけじゃないんですけど、もっと振り切ったら、どうなるかな?って。
露崎:たしかに振り切ってる、この曲はね。- ――成田くん以外の3人はクラシックとかは、どんな感じなんですか? 触れてきたりするとか。
露崎:いやー、そんな言えるほどのものは……(笑)。
大胡田:私もピアノはずっとやってましたけど、成田さんの前で、あんまり「ピアノやってた」とか言いたくない。
一同:あははは!
三澤:僕も、聴くのは好きでしたね、昔は。ショパンコンクールで優勝した、みたいな人が地元に来たら、必ず見に行ってました。
成田:あ、そうなの!? 初めて知った。
大胡田:意外だねえ(笑)。
三澤:全然、自分で演奏したりはないんですけど。だから、この曲がきたときは、けっこうニヤッとしましたね。
大胡田:え、だからメタルが好きなの?
三澤:そこは影響してると思うよ。
大胡田:そこらへんもクラシックの要素があるからね。- ――メタルはゴスペル的な雰囲気が入ってたりする曲もありますもんね。
三澤:なので、そっちの感じで弾きたくもあったんですけど、やっぱりギターって、曲の方向性とか、ジャンルを決めちゃう楽器だったりもして。そこらへんはすごく悩みました。
- ――今日は三澤くんの新たな一面を知れる日だなあ。ギターを弾くのを辞めてみるとか。
一同:あはははは!
- ――次、「人間合格」です。これ、好き。
大胡田:私も好きです!
- ――パート2。
一同:あはははは!
- ――大胡田さんの歌詞。“形だけ人間 心なんて嘘”。これまた俺が反省するんですよ。
大胡田:また反省させた(笑)。
- ――自分が良いことしてるとか、優しくしてるとか、そんなの嘘で。俺って……みたいな。
成田:なんかどんどん大胡田が説法してるみたい(笑)。
- ――なんかね、大胡田さんの詞には教示を受けるんですよ。自分が慢心して生きているのを、しっかりキュッてしてくれる感じがする。それは「まだら」もそうだけど。 歌詞を見たときに、「これはどういう曲なんだろう?」って、我々リスナーは想いを巡らせるんですよね。結局、正解にはたどり着けないんだけど。なんか自分と作った人とが接する部分を見つけようとするというか。
大胡田:うんうん。
- ――でね、よっぽど大胡田さんは自分に厳しい人なんだろうなって思う。
大胡田:いや、でも何て言うのかな。自分で歌詞を書いててあれなんですけど、言葉って、そんなに信じていいものじゃないなと思ってて。人間って、いろいろなものが入ってる皮の袋だと思ってるんです(笑)。 すごいね……見やすくてわかりやすくて、過信しそうになるんですけど、結局大事なのは心の部分で。私たちだったら、「伝えたい」とか「届けばいいな」みたいなところがいちばん大事なのに、外側ばっかりで生きてて、 かたちだけ人間だなって思うんです。これは本当に私のことでもあるんですけど。いつか「人間合格」っていう歌詞を書きたいなと思ったんですよね。
- ――聞けば聞くほど、俺、全然合格してないなあ……。
成田:説法モード。
大胡田:なんか……すいません(笑)。- ――大胡田さんの歌詞とか声って、勝手に神とか仏みたいなのを感じるんですよ。
成田:人ならざる感じ?
- ――そして、ありがたきもの(笑)。ライブのパフォーマンスもそう。登場するときに、ガネーシャ的な感じもするし。俺だけですか?
成田:いやいや(笑)。大胡田はそういうモチーフが好きだもんね。ガネーシャって言っていいのかわからないけど、インドのほうなのかな?
大胡田:シャーマン的なね。- ――次の「tika」の読みは「チカ」ですか?
成田:これ、「ティカ」って読むんですよ。
- ――俺、最初はティカって読んでたの、頭のなかで。でも、歌詞を見たら、“チカチカ”って書いてあるから、チカなんだと思ったら。
大胡田:わかりづらくて、ごめんなさい(笑)。
成田:どっちでもよかったんですよ、本当は。でもティカにしようって。- ――メモによると、「ここでいったん安心」って書いてあります。もうひとつのパスピエのカーニバル的な要素、お祭り的な型なのかなと。あと、フレンチテクノっぽい。
一同:おー。
成田:この曲は、最初はけっこうイントロも全然違う構成で、ワンコーラスだけ決まってて。……5〜10年ぐらい前かな、EDMとバンドサウンドがめっちゃ近かった時期があったじゃないですか。日本でも四つ打ちが主流になって。僕らもその真っ只中に活動してきたバンドではあるんですよね。シンセでガーッて上がる。そういうサウンドに和の要素を入れたいなって、ふと思って。音色的には三味線とか尺八を入れてたりするんです。
三澤:民族感はすごいよね。どっちの方向にもいけそうな曲だったんですよ。バンドっぽくしようと思ったら、バンドっぽくもなるし。民族楽器の音を上げたら、そういう印象にもなるし。
成田:「どっちにもいけるし、どっちにいこうか?」っていうのは、すごくパスピエ的に1個軸にしてるところですね。どっちに聴いてもらってもいいというか。
三澤:特に今回のアルバムは、そういうのが多かったかもしれないね。
成田:うん。やっぱりね、リズム楽器がメンバーにいないぶん、「自分たちをバンドって呼んでいいのか?」って思った時期もあったんですよ。メンバーだけで完結してるわけじゃないから。誰かに叩いてもらったり、コンピューターで打ち込んだりするなかで、なるべくバンドサウンドにしようとか、めっちゃ打ち込みのほうにやってみようとか、紆余曲折した時期はあったんですけど。いまね、わりと、「あ、こういうことをやったら、どっちにも楽しんでもらえるかな」っていう居所を、なんとなくこのアルバムで見えてきたところはありますね。- ――これ、“「冴えて仕方ない」”って歌詞が超いいよね。
大胡田:サビ前にそれを差し込んで、サビでキマってもらうっていう(笑)。
- ――これはお祭りの曲だったから、反省はしなかった。
大胡田:よかったです(笑)。
言葉って、そんなに信じていいものじゃない。人間って、いろいろなものが入ってる皮の袋だと思ってるんです(笑)。(大胡田)
- ――最後、「つむぎ」。いちばん好きかも、パート3です。これはもう「イントロ選手権」があったら必ず優勝するっていう。最後にやられました。
成田:この曲はずーっと昔からあって。リリースしてこないままだったんですよ。
- ――そうなんだ。
大胡田:ずーっと前だよね。
露崎:そうだね。
成田:いろいろアルバムの曲をまとめていくなかで、最後の曲って、すごく考えるんです。いまはストリーミングだったり、いろいろな音楽の聴き方があるなかで、最後の曲になればなるほど、どうしても日の目を浴びにくくなっている。アルバムの10曲目って、そういう立ち位置の曲順だと思うんですよ。だけど、そこで自分も気を抜いたら終わるなっていうか。
三澤:そうだね。
成田:だから最後に何の曲で締めようか、みたいなのはめちゃくちゃ迷って。候補3つぐらいまで絞って迷ったんですけど、最後の最後でこの曲にしようって決めました。
大胡田:これはもう最後の曲って決めてやりはじめたからね。
成田:ただオーバーグランドなだけの曲にするのはなんか違うなというか。ちょうどいい温度感って何だろう?っていうなかで選んだ曲ではあるんです。- ――俺は完全に盤あり世代だから、アルバムは1曲目から最後まで流れで聴くのね、だから、「人間合格」で、人間に合格しなくて、だけど、「tika」で、お祭りで踊って救われる。それが、最後に「つむぎ」があることで締まるんだよね。で、1個また歌詞問題があって。
大胡田:何だろう?
- ――“さめなかった夢を見てる 目を開けても消えなくて”のところ。どういうこと?と思って。
大胡田:これは自分たちのことですね。夢っていうのは、私たちのやってることであって。頭のなかだけじゃなくて、現代に、こうやって存在して、音楽活動ができていて、そのなかで出会ったものが、どんどん続いていくんですよ。 だから、「目を開けても消えなかったもの」っていうのは、私たちの夢とか目標っていうのが、かたちになってるいまのことで。
- ――あー、そっか。俺、マイナス思考なんで……。
大胡田:(笑)。
- ――目をつむってるときには、いろいろ嫌なものが見えてたの。俺の頭のなかでは。でも、大丈夫、目を開ければ、なくなる。……と思ったら、目を開けても、まだある!っていう。
一同:あはははは!
- ――マイナス思考が聴くと、そうなる。
大胡田:まあでも、そういう流れでもとれますけどね、うん(笑)。
- ――そこは答え合わせをする必要は絶対にないし。
大胡田:そうですね。音とか、私の歌詞もそうだけど、いろいろな取り方をしてもらっていいから、自分たちで答えを出さない状態でお渡ししたい。全部の曲がそうじゃないですけど。受け取った方のところで何か感じてもらえたら、それでいいのかなって思いますね。
- ――やっぱり作り手にとっては、作ってかたちにするところまでがピークというか?
成田:そこはいつも不思議な感覚ですよ。1回そこでピークに達して、「よーし、録ったぞ」ってういところがあって。でも、そこからリリースされるまでって、2ゕ月、3ゕ月、下手すれば、半年ぐらい空くときもあるから。なんかこうね、1回また自分たちで思い返すとか。
露崎:そうだね。
大胡田:いま、このアルバムができて、私たちがやってる音楽って、さっきの成田さんが言った承認欲求の話で言うと、「他人からの」っていう部分が変わってくると思うんです。
成田:一般からの承認ってこと?
大胡田:そうそう。承認のされ方も変わってくるよなって。成田さんの話を聞いて思ってた。
成田:そうだね。このコロナ禍がどれだけ続くかでも、音楽の聴き方だけじゃなくて、作り方も変わっていくだろうなとも思うし。でも、そのときに出すべき音楽が、そのときの正解でしかないから。そこは不思議なもので。エンタメって、改めて面白いなと思いますけどね。- ――たしかに。僕もラジオ番組作っているじゃない?やっぱり普段聴いてくれる人が喜ぶことをやるべきなのか。本来はノンリスナー含め広く届けないといけない、そういう番組作りをしなければいけない。 じゃないと前に進めないと思うんだよね。自分の中でこれをやったら面白いと思うものとの折り合いというか…
成田:結局、ゴールはひとつなんですよね。自分で渾身の作品を作って認められたいっていうことでしかない。でも、そのプロセスもどんどん細かくなってるし、見られ方も変わってくるし。 その切り取られ方次第でね、反対意見のほうが大きくなってくることもあるし。そのなかで、作る側の気持ち的なものはね、普遍でいたいなと思いますけど。
- ――ああ、「普遍」ってわかる気がする。いままでパスピエが出してきた曲を聴いてると、あ、なんか普遍だなって感じることがすごくある。
成田:そう、そこはね、すごく声を大にして言いたい。前作今作から聴くと、「あ、違う」と思うかもしれないんですけど、ずーっと聴いてくれれば、1個の何かにはなってるはずだから。
- ――そうだね。パスピエって、みんな電子楽器でしょ?
露崎:はい。
- ――だけど、すごく手作りな感じが伝わってくるんですよ。だから、ライブがすごいと思えるんだよね。難易度高いことを、みんな涼しげな顔でやるでしょ?
成田:たぶん全員不器用なんですよ。結局ね、全員、表面上は違うことを言ってても、みんなそれぞれ譲れない何かを持ってて。それこそEDMみたいな曲をやりましょうって言っても、絶対、四つ打ちでめっちゃダンサブルな曲一辺倒にはならなくて、僕らは。
三澤:うん。
成田:で、そこが、さっきの捻じれ的な部分にも通じるかもしれないけど、パスピエなんだろうなあって思うんですよね。- ――最初のほうに成田くんが言ってたけど、クラシックなり、ジャズ、フュージョンっていうのを、全部ポップスに変えてる感じがするよね。しかも、そのポップスがちゃんとパスピエじゃないとできないポップスになってる感じは、毎回聴くたびに、すごく思うことかな。
成田:うれしい。
露崎:「自分たちにしかできないことは何か?」っていうことはずっと考えてますね。結局、他がやってるようなモデルをまるまるなぞってしまっても、だったら、オリジナルを聴きましょうよ、みたいなことになってくると思うので。成田の作曲から出てくるものとか、4人のバランスの絶妙な噛み合い方を感じてもらって、それがパスピエっぽさだなって思ってくれたらいいなと思います。- ――なびかないよね。安易に飛びつかない感じというか。
成田:そうそうそう。
大胡田:「なびかない」じゃなくて、「なびけない」だよね(笑)。
露崎:どっか頑固なんですよね。- ――タイトルの「synonym」って、どういうことなんですか?
成田:「synonym」は「同義語」っていう意味です。「類義語」とか。今日話したこと全部につながることだと思うんですけど。断片的に切り取ると、違うじゃんって思っても、ルーツをたどると、同じだよねっていうことがめちゃくちゃあると思ってて。自分たちは、いろいろなことにチャレンジしてきたんです。四つ打ちとか、激しいロックとか、ちょっとフレンチポップなスタイリッシュなことをやりたいとか。でも、それは毎回なりたい目的が変わるってことじゃなくて、今年1年こういう音楽をできたらおもしろいなと思って、それを具現化したら、こうなりましたっていうことで。それは音楽をはじめたときから変わってないんです。で、それを、伝えるのは「類義語」かなって思ったんですよ。英語だと、つづりも回文っぽいところがあって。
大胡田:見た目がね。- ――12月25日はライブ(「synonium」)ですね。
成田:はい。
- ――俺、成田くんはサディストだと思ってて。
一同:(笑)。
- ――成田くんの作る曲を、ライブで具現化する周りのメンバーがすごいなあって思う。よく一緒にやってるなあって。素人目でもあんなに難易度が高そうなものを。
成田:まあ……バンド内でどっち寄りかって言われたら、サディスト寄りだろうけど(笑)。
一同:あはははは!
露崎:そうだね(笑)。
大胡田:成田さんは、自分に対してもサディストだからね。自分でも、「それ、弾く?」みたいなことをやってるし。ちょうどバランスがいいね。自分にも他人にも厳しい。- ――そうだね。自分がラクして、他人にだけやらしてたら、ダメだけどね。
成田:ふだんから偉そうなことを言ってるので、メンバーには(笑)。
結局、ゴールはひとつなんですよね。自分で渾身の作品を作って認められたいっていうことでしかない。(成田)